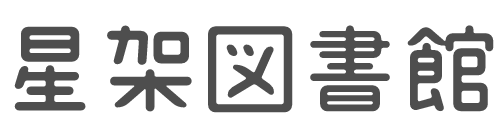天涯まで、傍にいて
波の音。それは静かな子守り歌でもあり、海を癒す歌。
ざぁ、ざぁ。孤独な色は音を繰り返し奏でている。それを、クヴァメルはぼんやり。眺めていた。
この頃、考えることが増えてきたのだ。楽しい悩みも、たくさんあるが。それよりもなにより。
クヴァメルの番である、ヴァーツのことだ。
自分達、幻獣種と呼ばれるものには、道の終わりなんてきっとなくて。
周りの人々が眠っても、きっと自分達は歩み続けるのだろう。
……それじゃあ、ヴァーツはどうなるのだろうか?クヴァメルは思う。
ヴァーツはきっとこれから先、自分と共に歩めなくなる日が来る。眠りについてしまう日が来る。それが。
それが、今のクヴァメルにとって、どうしても胸が締め付けられるようになってしまうものだったのだ。
「……なんで、幻獣種は死なないんでしょう」
ぽつり、ひとりごちる。きっと誰かに聞かれてたのかもしれないが、今のクヴァメルには関係がなかった。
ざぁ、ざぁ。それは子守り歌によって消えてなくなる。
時折、思うことがある。
もし、ヴァーツが、来世にここで生まれ変わってくれるのだとすれば。
自分は、来世のヴァーツまで迎えに行っても、いいのだろうか。そんなことを、クヴァメルは考える。
「お姫さん、何してるんだよ。こんなところで」
「……ヴァーツさん」
「メレアお嬢が心配してたぜ? クヴァメルがいないーっつってな」
ああ、あなたの声がこんなにも愛おしく感じるのも。
あなたの笑顔がこんなにも寂しくなるのも、ぜんぶ。ぜんぶ。
きっと、クヴァメルはヴァーツのことを、愛しているのだから、切なくなるのだろう。愛おしく感じるのだろう。
そうして、クヴァメルは口を開く。
「……ヴァーツさん」
「ん、どうした。お姫さん?」
「ヴァーツさん、あのね。私は、ヴァーツさんのことを愛しています。……だから、」
「……だから、ヴァーツさんが生まれ変わっても、一緒にいてもいいです、か」
ああ、言ってしまった。言ってしまったのだ。こんな重いこと、クヴァメルもわかっているというのに。
それでも、過ぎ去る時は待ってくれやなんてしないし、過ぎた言葉も待ってはくれないのだ。
少しの、沈黙と、ざぁざぁと子守り歌。やけにざぁ、と頭の中に響いたような気がした。
ほんの、少しだけ。ヴァーツの顔が見れないような気もして。目を伏せる。
「……お姫さん、や。クヴァメル」
「オレ、ここに来てから怖いくらいには幸せだよ。もちろんお義兄さん達もそうなんだけどさ、」
「何よりも、クヴァメルがいてくれたおかげなんだよ。だがら……」
「……来世でも、クヴァメルの王子様でいさせて、くれるか?」
ああ、なんて曇りのない笑顔。なんて純粋な笑顔なんだろう。
嬉しい、やら。ごめんね、やら。幸せ、やら。ぜんぶ、ぜんぶ。混じってしまって。
ようやく出た感情は、そのどれでもなく、一粒の涙、だった。
ヴァーツは、わかりやすくなんて慌てたりもして。それがクヴァメルにとっては全てが愛おしく見える。
「ふふ、大丈夫ですよ。これは嬉し涙です。そっか、そっかぁ……また一緒にいても、いいんだ」
「もしヴァーツさんがいなくなったとしても……私達は皆待っています。ずっと」
「そっかぁ、あんまり待たせないようにするな」
優しい声色がこんなにも、じんと熱くさせるものだなんて。
ヴァーツは、優しくクヴァメルを撫でる。暖かいぬくもりに、クヴァメルは安堵の笑みを浮かべたり、なんて。
なんだか、いつの間にかだが。
海の子守歌も、二人を祝福しているように思えたのは、きっと気のせいなんかじゃない。
クヴァメルは、ヴァーツの胸に飛び込んで、温もりに寄り添う。
きっと、自分が生きていた意味は、このひとと出会うためなんだって、そう思うくらいには。
幻獣種という種族は、健気で美しく、強い種族であるのだ。
あぁ、幸せだな。クヴァメルは、それを噛みしめながら、今はただわかりやすく照れているヴァーツに知らんぷりなんかをしてみせて。
泡にならない人魚姫も、確かにここに存在したのだ。
ざぁ、ざぁ。祝福の歌が聞こえる。