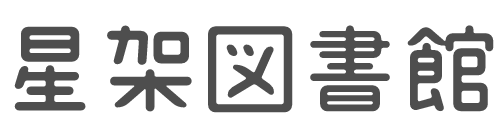君を飾る思い出たち
いつだったからか、その世界では聖夜祭などと呼ばれていた日がある。
始めて世界に星の祝福というものが与えられ、世界に生命の息吹というものが芽吹いた日だと、クヴァメルはそう記憶していた。
もっとも、そんな日があっても自分には関係のないものだと、そう思っていた。はずだった。
街が煌びやかな光で包まれ、空の祝福の光がやけに遠く見えたのが今でもやけに思い起こされる、記憶。
「サタン。知ってるよ、あの施しをもたらす謎の使徒」
まさか兄からそんな無知のような言葉が出てくるとは思わなかった……とクヴァメルはその時思ったそうな。
サタンじゃなくてサンタ。施しとはプレゼントのことか。使徒とはもはやどこから来たのか。
色々言いたいことはあったが、サンタと言う文化はつい最近囁かれているものだ、知らないのも無理はないと。そう思うことにした。
「おおむね、ヴァーツのことでしょ。最近のメルはヴァーツのことばかりだし」
「……さようでございます、」
「……で、何を頼みたい?」
そこで言葉を飲んでしまう。
こういう時の兄、ネヴァーレンはだいたいクヴァメルが何が言いたいかわかっていて聞いているものだ。
言葉はキツく感じるものの、声色そのものは特に嫌がっている様子はないと感じるのは、クヴァメルでも兄妹なものだ、と。
しかし、しかし。わかっているのならばわざわざ聞かなくてもいいのでは、と思うわけで。なんていじわるなことだろう!なんてことも。
クヴァメルには兄の意図なぞわからなかった。
でもこっちだって、譲れないものはあるのだ。何故ならば───。
「……兄さん。折り入って頼みがあります」
……というのが。クヴァメルでの、先程の話。
時は少し経ち。現在という時刻。
何故か面子が集められていたものだ。海帝であるオルティレイスを筆頭に。
もしかして、幻蒼十海柱案件のことを頼んでしまったのか?この時ほど強く思ったことはなかった。
妙に重たい空気。そして感情が読めない表情のオルティレイス。正直クヴァメルは帰りたかった。もうここが帰る場所ではある。
「話とは、なんだ」
ようやく沈黙を破った言葉。そんな神妙になるほどだったものか、サンタは。サンタのことだよね?
一体どんな様子でこんな状況を作ったものか、と気になりもするもの。
「……サタンって、知ってる」
「ネヴァくん、もしかしてサンタのことを言ってる?」
「施しを与える、謎の使徒なんだけどさ」
「ネヴァくん」
せっかくのルカレオスのツッコミの言葉を台無しにするほどのネヴァーレン。
これは正直、ルカレオスだけでもサンタとわかってくれて助かった。と、思った矢先。
オルティレイスからの言葉は、こうだ。
「ヴァーツか」
ん!?
クヴァメルを始め、誰もがその場にいた、全員が驚いていた。もう表情でわかる。
まさか、まさか。クヴァメルの名前ですらも最初の一文字以外は間違えるあのオルティレイスが。
ちゃんと名前覚えれるのか、と言う感情と、それならば自分の名前も覚えてほしい、と言う感情がクヴァメルの中で入り混じった。
当の本人は相変わらず感情が読めない。が、「どうした」とは言いたげではあることはわかる。
どうしたもなにも、今まさに海に星の祝福が施されようとするようなことが起きているのだ。
「……ああ、うん。そう、ヴァーツ。オルフィってサタンのこと知ってたんだ?」
「サンタだよネヴァくん」
「噂程度には聞いている。それで、サタンに望むものはなんだ」
サタンじゃなくてサンタ。お前もかと言いたい気持ちは存分にあったがこらえた。
そこでネヴァーレンはクヴァメルに目線をやる。
静かに、深呼吸。クヴァメルは眼差しを前に向けるものだ。
ことの経緯。そしてサタン……サンタという存在をヴァーツにまた、思い出させたいということを伝えたもので。
再び訪れる刹那の沈黙。
そうしてそれを破ったのは今度はノエルメイアだ。律儀に片手なんて上げてみたりもする。
「……サタンとやらはいいのだが、やはり女性の部屋に入る以上クヴァメルが適任ではないか?」
「あー……うん、言われてみれば。あとヴァーツは勘がいいから、気配で僕達だとすぐわかるだろうね」
「メル、プレゼントは用意してやれるけど……あとは自分出来そうかい」
そこはクヴァメルも失念していた。しかしそれならば言い出しっぺゆえに、退くわけにもいかないのだ。静かにうなずく。
相変わらず、このひと達のことはまだよくわかっていない。が、悪いひとではないことも確かであって。
みんなしてヴァーツのことを考えてくれているのが、クヴァメルにとっては今更のように、それを感じて嬉しくなったりもした。
箱の色はどうだとか、やはりラッピングはなどもはやクヴァメルよりも盛り上がってしまっているのを、そっと逸らす。
昔と比べて色んなものを喪ってきたものたち。しかし今もまだ、確かにそこに在るものがある。
ヴァーツにも、それを少しずつ知ってもらえれば、クヴァメルとしては嬉しいと、そんなことを想うばかりだ。
無事、任務を達成できたクヴァメルのあとに、ヴァーツの反応を知ってみんなして喜んだことは、まだ本人にはないしょのはなしでもあった。